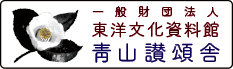夏の企画展「月光〜穐月明の夜の景色Ⅱ」
2025年7/20㈰~9/8㈪ 火曜日休館

穐月明は月光の下の美しい景色をたくさん描いています。月光に輝く水面や白く浮かび上がる雪や花、寺院や仏像は夜だからこそ其所に神秘的な空間がうまれます。今回はそんな作品を照明を消した暗がりの中、キャンドルライトで照しながら月夜の世界を体験していただきます。また、金屏風や仏像を暗いお堂の中のようにキャンドルで照し出す等、光りの演出を試みます。暗がりの中でこそ見えてくる光りと影のアートをご覧ください。
夏休みの工作「まわる灯篭をつくって、光りであそぼう」
様々な素材を自由に使って光りのアートを作ります。思い思いに描いたり、組み合わせたりしながら作った作品は、展覧会場に展示してみましょう。
【開催日】7月26日㈯、27日㈰
【時 間】 10:00~12:00
【持ち物】ハサミ(使いやすいもの)、カッターナイフ、定規、セロテープ、ステックノリ、鉛筆
【会 場】 伊賀市 ミュージアム青山讃頌舎 中庭及び展示室
【講 師】 上田慎二先生
【参加料】 500円、観覧料100円引き割引券付き
【お申込】 各回定員15名/小学生以上(保護者等同伴可)
【申込受付/お問合せ】 青山ホール ☎0595 52 1109
ギャラリートーク「夜の景色」
暗闇の会場の見所を紹介します。
【開催日】8月9日㈯、8月23日㈯
【時 間】13:30~
【お申込】不要(観覧料のみ必要)
【解 説】当館学芸員 穐月大介
近郊ハイキング「名峰 伊賀富士・尼ヶ岳に登る」
関西100名山に数えられる伊賀の名峰尼ヶ岳に登ります。標高は957.4mも有りますが上り口が536mなので比較的短時間で登れます。伊賀富士と呼ばれる通り独立峰の元火山です。
【コース】尼ヶ岳登山口~尼ヶ岳山頂/昼食~尼ヶ岳登山口(徒歩約5km・3時間)
【開催日】9月6日㈯10:30~15:00
【集 合】10:30 尼ヶ岳登山口/伊賀市営南部簡易水道浄水場・駐車場(伊賀市高尾を南下桜峠方面へ)
*集合場所の分からない方は伊賀市ミュージアム青山讃頌舎受付10:00までにお出でください。
【案 内】伊賀市ミュージアム青山讃頌舎 学芸員 穐月大介
【参加費】300円(観覧券付き) 定 員:先着15名
【持ち物】お弁当、飲み物、雨具、暴風・防寒着等
【申 込】青山ホールTEL 0595-52-1109で受付
月光〜穐月明の夜の景色Ⅱ
展示室を暗室にし、LEDキャンドルだけで照明しています。

受付でキャンドルをお渡ししますので、照しながらご覧ください。

穐月明/想い出 喧嘩両成敗
キャンドルで見ると明るい所で見るのとは全く違う臨場感を感じます。

キャンドルが並べられた幻想的な展示室。

穐月明/月下枝垂れ桜
月光に照された夜桜です。

穐月明/野の仏
月の下で瞑想する観音です。下に置いてあるのはアメジストのジオードに入った金銅仏です。

菩薩立像/金銅仏 中国古代
アメジストジオード
中国古代の金銅仏です。仏像の鍍金はロウソクなどで見ることを想定しているようで、とても美しく輝きます。

穐月明/鹿と御堂
奈良公園の鹿でしょう。

上 絵画 穐月明:左 普賢菩薩、中央 釈迦如来(遺教経)、文殊菩薩
下 仏像:中央 釈迦如来坐像/木象 江戸時代、左右 普賢菩薩・普賢菩薩/新歓嗣 陶仏
お寺のお堂のように仏像をロウソク(キャンドル)の光で見ていただけます。

仏像はロウソク〈キャンドル)で見ると金色が輝き金屏風がより荘厳な雰囲気を醸します。

穐月明/左 月明の川、右 月の小川
こんな夜道を歩いたことはないでしょうか?とても美しい月夜です。

穐月明/我愛山中松
「わが愛す山中の松」は宋の詩人真山民の漢詩です。人知れず立つ山中の松も月は照します。

チェコ硝子 水差
表千家13代家元・即中斎の花押が有ります。チェコガラスの器を即中斎が水差しに見立てたようです。深いカットのガラスがキャンドルライトを透過して美しく光っています。

穐月明/月光貼雑屏風
色々な月夜の景色を風炉先屏風にしています。回っているのは走馬灯です。
ミュージアムの受付でミュージアムオリジナルグッズや図録を販売しています

。オリジナルグッズを紹介⤴️ペーパーグライダーや竹蜻蛉の型紙もダウンロード出来ます。
今後の展示予告
*以下の予定は変更されることもございます。
2025年
❹9/20㈯〜10/31㈮ 「桃山文化と現代アート」
桃山時代の作品には現代アートに通じるものがある。京都市立芸術大学の協力で桃山時代の美術品と現代アートのコラボ展。
・木の実を食べる「カレーとデザート」
❺11/12㈬〜12/15㈪ 「パラミタミュージアム名品展」
パラミタミュージアム所蔵絵画「横山大観」「川合玉堂」「川端龍子」を展示
伊賀市ミュージアム青山讃頌舎10周年企画
2026年
❻1/8㈭〜2/15㈰ 「伊賀市 藤堂豊前家の遺品」
伊賀市文化財課による伊賀市の文化財の公開展示。
❼3/5㈭〜4/6㈪「穐月明の四国八十八所の旅」(土佐編)
穐月明の大作「四国八十八所の寺と仏」の内「土佐編」の初公開
2026年度には伊予編も展示も予定
・春の呈茶会
・ハイキング常福寺「八十八所めぐり」
過去の展覧会
特別展「化石が語る太古の世界」
古琵琶湖層群と中新世の地層が遺したもの
2025年6/7㈯〜7/6㈰
化石に興味を持ち始めてはや60数年
生まれ育った地が、古琵琶湖層群と中新世(阿波層群一志層群)の地層に囲まれているという恵まれた環境の中、暇を見つけて採集した化石たちを展示いたしました。
琵琶湖博物館企画展示室で、2001年に参加して以降、伊賀盆地化石研究会として、地元で数多くの展示会を開催してきました。
コツコツと採集してきた私に大地から最高のプレゼントがありました。
それは、ナマズの頭蓋骨化石です。
今回、伊賀市文化都市協会様よりお声がけを頂き、ナマズをおまつりしている地震よけの大村神社の側で私の化石人生の集大成として展示会をさせて頂く事に、深いご縁と喜びを感じております。
伊賀盆地化石研究会 北 田 稔

春の企画展 「絵本のような絵画展〜穐月 明の絵から始るおはなし〜」
2025/4/19日㈯〜5/26㈪
穐月作品の多くには元になった話が有ります。古典や禅のむつかしく思える話でも、読んでみると面白い物を題材にしています。今回の展覧会ではそんな絵の元になった話を童話のように楽しく読めるお話にしました。細かいニュアンスや表現は正確ではないかもしれませんが、こんなおかしなお話なんだなと、絵を観ながらお楽しみいただけたら幸いです。おとぎ話有り、伝記有り、説話有りの絵本のような展覧会です。

春の通常展「四季折々ー穐月明の花と木と」
2025/ 3/1 ㊏~ 4/10 ㊍
穐月明は水墨画家を目指すようになってからそれまでの個性的な作風から自然の美しさをあるがままに表現する画風に向かいました。それは自身が幼い頃から親しんでいた仏教観から無為自然がやはり美しいと言う思いに至ったのでしょう。
それゆえ花や木をこよなく愛し小さな野の花も見逃さず、その美しさ、たくましさ、やさしさを在るがままに描き、時に主役に、時にやさしく作品に花を添えました。そんな四季を通じて描かれた植物をご覧ください。

新春企画「新 歓嗣―作陶60年の軌跡―」
歓嗣 × 穐月明コラボ展
2025.1.10㊎―2.10㊊
この度、青山讃頌舎にて私の作陶六十年の作品を展示させていただくことに成りました。
その時代に創りたい物をジャンルを問わずひたすら制作して参りました。生前、若輩の私に親しく接して頂いた敬愛する穐月明先生の絵画(軸)も同時に展示して頂ける光栄に感謝申し上げます。
陶芸家 新 歓 嗣

秋の通常展「浜辺の四季〜穐月明が描く海〜」
2024/10/31 ㊍~ 12/20 ㊎
穐月明が少年時代を過ごした故郷 実報寺は愛媛県西条市の海に近いお寺で、浜には大きなカブトガニが生息している自然と文化の豊かな所でした。それゆえか海の作品にはなにかしらの故郷への思いが反映されているようです。
夏の穏やかな海、冬の荒海、月夜の海、海にまつわる和歌や物語を描いた作品など海を描いた作品には、得意とした清らかな理想郷のような山河作品とは違う力強さや荒々しさを感じさせる作品が多いようです。
大きな海原とそこに広がる波と光り、そしてそこにも有る人の暮らしをご覧ください。

秋の特別展「のぞいてみよう源氏物語の世界」
令和6年9月1日㊐~10月14日㊊
紫式部によって著された『源氏物語』は、およそ千年の時空を超えて読み継がれ語り継がれ、各時代にわたってさまざまなかたちで享受されてきました。しかしながら現在の我々にとって『源氏物語』を理解するのはハードルが高いと感じる人も多いのではないでしょうか。本展覧会は、そんな『源氏物語』の世界を少しでも身近に感じていただくために企画しました。特別展示として当時の十二単などの装束を展示し平安の美を体感していただけます。

夏の通常展特別企画、暗がりの中、キャンドルライトで見る展覧会「夜の景色/穐月明の月と星と」
開催期間2024/7/6㊏~8/18㊐
照明を消した会場の暗がりの中でキャンドルライトを照らしながらご覧いただきます。夜はとても美しく神聖で少し怖い時間であり、月や星は神仏にたとえられていました。そんな美しい夜を穐月明はたくさん描いています。今日、日常で夜の暗がりを体験することは少なく月星を楽しむことも少なくなりました。この度、暗闇の中で作品を見ていただくことで夜の神秘的な美しさや暗がりで見る仏像の荘厳さなどを体験していただきます。

初夏の企画展新指定 伊賀市文化財 若宮八幡神像 初公開「神が息づき仏が導く~穐月明と仏教美術の世界」
2024.5/17 ㊎~ 6/17 ㊊ 火曜日休館
故穐月明旧蔵の古美術は伊賀市に寄贈されたものの評価が定まっていませんでしたが、その一つ「若宮八幡神像」が昨年、伊賀市の文化財指定を受けました。その公開に合わせて、生涯を通し集めた仏教美術の優品と神仏をテーマとした作品を展示し、穐月明が見ていた神仏の世界をご覧いただきます。また、隣接する大村神社・虫喰鐘も昨年、伊賀市文化財に指定されました。虫喰鐘は大村神社の神宮寺であった禅定寺の鐘だったものです。禅定寺に関わる文化財を同時に紹介し地元に残る神仏の世界の一端を紹介致します。

日根野作三展 SAKUZOHINENOEXHIBITION
伊賀が生んだクラフトデザインの先駆者―地元に遺したものー
2024.4.13㊏ -5.6㊊㊗ 火曜日休館
「戦後、日本の陶磁器デザインの80%は日根野氏がつくられた。」これは人間国宝の濱田(ハマダ)庄司が、日根野作三に送った生涯を陶磁器デザインに捧げた日根野氏の活動の広さと奥深さに対する称賛の言葉である。

伊賀市 ミュージアム青山讃頌舎 春の通常展
「春を楽しむー穐月明の花と新緑」
2024/3/8(金)~4/7(日)火曜日休館
穐月 明の花の作品はありのままの美しさを実物以上に描いて大変人気がありました。木々が芽吹き花が咲き始める美しい季節に、花と新緑の絵画展を開催致します。

伊賀市 ミュージアム青山讃頌舎 新春の企画展
「絵が先か、俳句が先か」
令和6年1月13日(土)〜2月18日(日)㊊火曜日休館
穐月明作品を芭蕉の俳句と共に鑑賞する企画展を開催いたします。俳句から連想される光景と絵画から連想されるシチュエーションが響き合いどのような世界が見えてくるのか? お楽しみください。あなたが鑑賞するのは「絵が先か、俳句が先か。」

2023年 秋の通常展「流水頌歌/ながれのうた— 穐月 明 最後の思い —」
令和5年 10/21㊏~12/25㊊火曜日休館
穐月 明は晩年、風景画の作成に注力します。山間から海に至る水辺の風景を、ただ美しいだけではない、人と自然の営みとして描き「流水頌歌」として発表します。
そこには生涯仏教を探求し続け到達した、自然と調和した暮らしへの願いを強く感じます。力の衰えを感じながらも本当に描きたいものを追求した最後の個展の再現を試みました。

2023年 秋の特別展「魂の相剋 中野英一遺作展」
中野英一さんのこと
毛利 伊知郎(もうり・いちろう 三重県立美術館前館長)
中野英一の逝去から既に18年。今や彼の名と作品を知る人は限られているだろう。しかし、中野は20世紀後半の三重の美術界で逸することができない作家の一人だと思う。(以下略)
2023.9.8㊎ー10.9㊎㊗ 火曜日休館

夏の通常展「ちょっと笑えるアート展」
穐月作品には様々な魅力が有ります。本物以上に美しく描かれた花、清々しく平和な風景、優しく微笑む仏や石仏などどれも素晴らしいのですが、そこにちょっとユーモラスで可愛い表現が加わることも魅力です。
ほんとは怖い神様も偉いお坊さんも絵の中ではひょうきんでちょっと可愛く描かれます。美しい花や深淵なテーマの作品の中によく見るとユーモラスな人物や動物が入っているのを見つけると嬉しくなります。
今回は、そんなユーモラスな部分に焦点を当て展示致します。
夏のひと時、涼しいミュージアムで楽しいひと時をお過ごしください。
7月14日(金)~8月27日(日) 火曜休館

夏の特別展「福 郎」上田 保隆展
上田保隆(かみた やすたか)は伊賀の最奥の山村・霧生でフクロウにこだわり描き続けた画家です。
今回の展覧会は生前考えていたと言われる「夜の森」のようなイメージで展示しました。フクロウのいる神秘的で美しい夜の森のをお楽しみください。
2023年 6/2㊎~7/2㊐

春の通常展「あおやまのうた/青山讃頌—やさしい水墨画・あきづきあきら傑作選—」
当館所蔵の千点近い穐月 明作品の中から特に優れた物や過去の展覧会で好評だった作品を展示いたします。
2023.4.21㊎~5.21㊐

春の特別展「文化の交差する所 伊賀 ー出土品が語るその歴史と文化 ー
伊賀市文化財課の構成による当館初めての本格的な地元の考古展示となりました。
2023.3.10(金)〜4.9(日)

新春通常展「動物大好きー穐月絵画に登場する動物たちー」
穐月明の水墨画は従来の水墨のイメージにはない、優しさと可愛さがあります。特に作品に登場する動物たちには作者の特別な愛情が感じられます。
2023年 1/6㊎~2/6㊊

秋の通常展「西国三十三所の寺と仏」
新たに入手した穐月明「西国三十三所」作品二十点と新収蔵品を公開
2022年 10/21㊎~12/25

秋の特別展「谷本景の軌跡―The trajectory of Kei Tanimoto―
2022年 9月2日(金)~10月10日(月)

石仏の画家 穐月明
2022年 6/3㊎~8/22

穐月明の愛した仏–龍谷ミュージアムのガンダーラ仏 里帰り
2022年4月22日㊎~5月22日㊐

花を愛でるー穐月明の花と収集花器
令和4年3月18日㈮〜4月3日㈰

穐月明の水墨と現代漆芸の美
令和4年1月7日㈮〜2月6日㈰

こんなに楽しい四大絵巻物
2021/11/12-12/19

ー古伊賀憧憬ー小島憲二の眼と手
2021/10/1(金)〜10/31(日)

伊賀に暮らして〜穐月明の身近な風景
2021.5.21(金)~6.20(日)
7.22(木)~8.22(日)

没後10周年記念 榊莫山展-故郷・伊賀に帰る−
2021.4.16~5.6

春のやすらい−穐月明の水墨世界−
伊賀市 ミュージアム青山讃頌舎2021年春の通常展

美の視点ー穐月明の収集古物を紐解くー
伊賀市 ミュージアム青山讃頌舎2020秋の企画展展

伝承・創造伊賀焼展 伊賀焼『今昔』
伊賀焼伝統技術保存会第5回会員展
2020.8.8㊏―8.30㊐

2020年オープニング記念
「穐月明名品展・やすらう世界」
開催期間:2020年6月3日(水)〜8月2日(日)