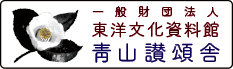日根野作三展 SAKUZOHINENOEXHIBITION
伊賀が生んだクラフトデザインの先駆者
―地元に遺したものーは5月6日終了しました。
2024.4.13㊏ -5.6㊊㊗ 火曜日休館


◆GALLERYTALK1
「伊賀における制作」
日 時 4月20日㊏ 13:30~
会場 青山讃頌舎 展示室
講 師 髙曽由子 (三重県立美術館学芸員)
定 員 各回15名(予約制)
◆GALLERYTALK2
「思いつくままに」
時 4月27日㊏ 13:30~
場 青山讃頌舎 展示室
師 小島憲二(陶芸家)
員 各回15名(予約制)
◆日根野正美代の茶盌を中心に聴樹庵「茶」を嗜む
日根野正美代の創作茶盌の中からお好きな茶盌を選んで気楽にお抹茶一服を召しあがれ。
日 時5⁄3㊎㊗・5⁄4㊏㊗・5⁄5㊐㊗
①10:00~ ②11:00~ ③13:00~ ④14:00~
会 場 茶室「聴樹庵」
定 員 各回8名(予約制)
呈茶代 400円(お抹茶・お菓子)
[お申込み・受付]
午前10時から青山ホール電話0595-52-1109番にて申込受付開始

「戦後、日本の陶磁器デザインの 80%は日根野氏がつくられた。」これは人間国宝の濱田(ハマダ)庄司が、日根野作三に送った生涯を陶磁器デザインに捧げた日根野氏の活動の広さと奥深さに対する称賛の言葉である。
現在の伊賀市西高倉に生まれ(1907-1984年)東京高等工芸学校(現千葉大学工学部)に学んだ後、小森忍の山茶窯(ツバキガマ、瀬戸市)にデザイン担当として務める。1933年、小森と共に国立京都陶磁器試験所に入所、デザイナーとしての才能を開花させました。また「茶碗とは何か?」の思考を「茶碗とは、茶を点てる適当な凹をもち、片手で操作できる芸術的に格調の高き抽象刻である」と定義づけ、戦後の楽茶盌製作へと昇華されていきます日根野氏の最大の魅力は日本陶磁振興会の発足 (1947年)と共に、京都・四日市・信楽・美濃・瀬戸・常滑・遠く益子にも指導に赴き、戦後のものづくりの機械化が進んだ時代に対抗するため、各陶業地の窯元・作家・それぞれの作り手の得意とする技術や個性・地域それぞれの特性を活かした指導はデザインにおける人間性の復興を目指すもので、昨年三重県立美術館で催された、日根野作三展(2023.7.1-9.24)は、日根野作三氏の生涯をたどる、過去最大の素晴しい回顧展でありました。
今展は、地元に残る楽茶碗・佐那具陶磁器研究所の作品を中心に展示いたします。尚、日根野作三の生涯に亘る業績の資料は、多治見市美濃焼ミュージアムで保管されております。
陶芸家 小島憲二

伊賀焼をモダンにデザインした皿


佐那具陶磁器研究所【万歴五彩七角獅子摘蓋物】
真っ白な白磁・美しい青花文・鮮やかな五彩の細かな文様と7角形と言う複雑な形状を正確に造形した高度な磁器です。
文様は「甕壊し」。子供の頃の司馬光が、水の入った高価な大甕に落ちて溺れそうになった子供を、石で割って救ったと言う古事です。司馬光は高名な宋代の学者・政治家です。
【財団法人佐那具陶磁器研究所(府中窯・陶研)】
昭和16年(1941) 大阪市の陶磁器愛好家 木村貞造氏の支援により設立。所長・理事長 小森忍、スタッフとして日根野作三、澤田米三(痴陶人)ら有能な人材が揃い中国の古作品を中心(来代の青磁、明代の五彩磁、青花など)に製作を行なっていたが、太平洋戦争中であったことや独立採算制であったため、経営難により昭和23年頃には閉鎖(昭和25年?)。
小森忍、日根野作三両氏は昭和18年に退所となるが、相談・指導は閉所まで時々行なっていた様子。尚、一般向けの製品には「府中窯造陶研・府」及び美術工芸品には「文彬亭造」の四文字が印されている。・少数ではあるが「棅燭亭造」印の製品も見る。

高級中国磁器の写しの香炉です。

真っ白な生地と濃く鮮やかな青が美しい白磁です。
文様は佐那具陶磁器研究所オリジナル柄「ワニ」です。

さまざまな国のデザインを取り入れた陶磁器が並びます


戦時下の作品です。飛行機や戦車、軍艦などが描かれ「ハワイ攻撃」「マレー沖会戦」「シンガポール侵攻」等、先勝のシーン名が書かれています。戦勝の皿だったようで、当寺の時代を写す貴重な資料です。


【日本陶磁振興会】
終戦の翌年1946年日本農村工業振興会として将来の日本を背負う若者に技術教育をする為に設立されたもので、陶磁文化の振興をはかる陶業部門も含まれていた。翌年に組織は改められ日本陶磁振興会となる。所要の地に指導員を派遣し、作陶の改善技術の指導を行うことを目的とする。九州方面が水町和三郎、北陸が石黒宗磨、瀬戸が小山富士夫、美濃が荒川豊蔵、そして京都・信楽・四日市が日根野であった。その後、荒川、石黒は陶芸家に専念後に人間国宝に、小山も陶磁研究家・陶芸家となり、日根野だけはフリーの陶磁器デザイナーとして最後まで各窯業地を回りデザイン指導を継続した。

モダンなデザインの徳利です。戦後、日根野が陶磁器のモダンデザインを開発していった一つです。



石黒宗麿(人間国宝)【木の葉天日茶碗】、荒川豊蔵(人間国宝)【粉引酒器】、小山富士夫(陶芸家)【梅華皮茶碗】

日根野自身が自ら作ったユニークなデザインの楽茶碗が並ぶ

自画像が描かれた楽茶碗


右上に「HINENO」の文字と自画像が描かれ、中央下二波「1974」「こんにちわあかちゃん」の文字が書かれています。


パナソニック工場の記念皿とそのためのデザインです。