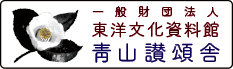5月26日㊐■文化財を訪ねて「大村神社と阿保宿周辺ウォーク」を開催
初夏の企画展「神が息づき仏が導く~穐月明と仏教美術の世界」のイベントとして阿保周辺の文化財を巡りました。
【日 時】 5月26日㊐
【行 程】 徒歩/伊賀市 ミュージアム青山讃頌舎~大村神社~柏尾~寺脇宝厳寺~初瀬街道交流の館 たわらや~伊賀市 ミュージアム青山讃頌舎
【案 内】 学芸員 穐月大介
気持ちの良い初夏の田園を普段見られない文化財や、余り気付かれない文化財を見ながら和やかに歩く事ができました。ありがとうございました。

大村神社の虫喰鐘
昨年、伊賀市指定文化財になりました。魔鏡を鋳込んだため乳がぼろぼろ落ちたと言う伝説の有る鐘で地元で鋳造されました。

国・重要文化財宝殿と本殿
宝殿の前で金山宮司さんに解説頂きました。桃山時代の様式を残す素晴らしい宝殿ばかりではなく、本殿も明治以降の建設ではありますが文化財レベルの優美な建物です。

柏尾・役行者石像
崖の上に祭られた役行者の社です。女人禁制だそうですので男性が代表して写真を採りに行きました。

柏尾・庚申地蔵
伊賀では青面金剛像が多い庚申塔ですが地蔵石仏が庚申塔として祭られています。柏尾には1mを超える銅鐸が出土したり、鎌倉の懸け仏が残っていたり古い歴史と文化財が多く残っている所です。

宝厳寺・重要文化財十一面観音
宝厳寺では遠藤住職に重要文化財十一面観音を見せていただき解説頂きました。この仏像は大村神社から神仏分離の時、移された物です。ここには同様に大村神社から移された大般若経などが収められています。

宝厳寺・本堂
本堂で住職さんから、水晶の玉に入った本尊の事や、宝厳寺の由緒についてお話し頂きました。

阿保・足止地蔵
道端に有り地蔵と呼ばれていますが閻魔様と十王蔵です。江戸末期村の若者が上野(街)へ出て行くのを防ぐために、閻魔様と十王蔵が見てるぞと置いたものと伝わります。当寺から都市への流出が問題視されていたようです。

たわら屋・参宮講看板
たわら屋で俵屋清右衛門姿の稲森さんから参宮講看板と伊勢参りの話をうかがいました。最近、参宮講看板を見に来られる方も増えたそうです。
この日のウオーキングがここで解散としました。