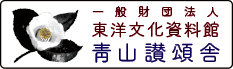伊賀市 宝厳寺の大般若経 | 展示初公開の歴史的な写経本
宝厳寺の大般若経(元大村神社 大般若経)は伊賀市 ミュージアム青山讃頌舎「神が息づき仏が導く」展で令和6年5月17日㊎~6月17日㊊まで公開されています。この大般若経が一般に公開されるのは今回初めてです。
寺脇宝厳寺の大般若経

これは現在寺脇宝厳寺が所有している大般若経の1〜100巻が収められた箱です。此のような箱が6つ有ります。
この大般若経六百巻写経本は元は大村神社の本殿(現宝殿)に収められていました。明治の神仏分離で大村神社の神宮寺・禅定寺が廃寺となったため「本尊十一面観音立像(国重文)」「三仏像・三神像木造厨子」共に寺脇 宝厳寺に移されました。その経緯は大般若経一巻奥書に詳しく書かれています。
神仏習合と神仏分離
江戸時代、神社には寺が、寺には神社が通常付属し神社と寺は一体として管理され機能していました。本地垂迹説的に言うと集落を守る氏神とその正体である仏と言ったイメージでしょうか。大村神社にも禅定寺と言う寺(神宮寺と言います)が有り現宝厳寺十一面観音(重要文化財)が祭られていました。それが明治になり政府から寺と神社を明確に分けるようにとの指示(神仏分離令)が発せられ神社に有った大般若経なども寺に移されました。しかし、それだけでは済まず民間レベルで排仏毀釈運動が起こり多くの寺が破却されました。伊賀のあたりはあまり排仏毀釈は起こらず多くの寺社がそのまま同じ敷地に存在しています。
大般若経の意味

大般若経はそれを唱える者も十六善神に守られるとされ、村々で購入し大般若会(転読会)が開かれました。右上に書かれている鹿島社は大村神社の事です。江戸時代には鹿島社として崇敬されていました。

穐月明「大般若経守護十六善神」
十六善神は玄奘三蔵が持ち帰った大般若経を守護する四天王と十二神将の事です。中央に釈迦と文殊菩薩、普賢菩薩、それを十六善神が囲み、玄奘三蔵(三蔵法師)と深沙大将(沙悟浄に当たる)が描かれ、大般若会に掛けられます。
大般若経の文字


大般若経第一巻の冒頭と三百三巻の冒頭です。文字が全く違い多く人が書き写した手書きの写経である事が分かります。
大般若経の奥書に書かれた由来

第一巻の奥書につぎのような由緒が書かれています。
「鹿嶋社 大般若経巻第一 伊賀国禅定寺 大般若波羅密多経第一」として、この経を南都(興福寺)真福寺で貞享一年に書写されたとあります。
続いて、「正徳元辛卯(1711)十二月十二日ニ興福寺東金堂の本一交畢 此巻先夏比より伊賀阿保禅定寺遺物以漸当月十日=返却□□□□□」と朱書きが有り。
経末に禅定寺から宝厳寺に移った経緯が書かれています。
「此経は禅定寺付経にして鹿嶋神殿に納めこれ有所、明治御一新の際、神仏混雑成ずとの事に付、引分て御本地仏(十一面観音立像と三仏厨子)と共に宮坊へ引取これ有所、其の内禅定寺廃寺に致し、それ故宝厳寺へ預り帰り、其後此の経文売払むとの事生じ、売払ならば先方注文の通りの代価にて宝厳寺住職其の代価に申受ける事に付、居る所氏子の内二三人程の乱亡人これ有にて案内これ無くして代金十円に外なる所へ売払致、それ故それこれと色々なる事の意論これ有、檀家一同打寄相談の上、此経 写経にて遺証の有る故に拠無当寺に有る板摺と取替、先方買主方へ相渡し此の写経を取替置者也」
要約すると、
・江戸時代、この大般若経は大村神社の本殿の中に納められていたが、維新政府の神仏分離令で別当寺であった禅定寺へ引上げられた。
・その後に始まった寺院整理で禅定寺は明治三年廃寺となった。
・その時、本尊十一面観音立像と三仏厨子は宝厳寺が預かることになっが、大村神社の氏子が大般若経を売却しようとしたので宝厳寺住職は「その値段で当寺が譲り受けよう」と申し出た。
・ところが、氏子の中の不心得者が勝手に十円で他へ売ってしまった。
・そこで、檀家たちが相談し、買主に交渉、当寺所蔵の木版の大般若経と交換ということで、ようやくこの由緒ある写経本を確保することができた。
と有り、此の経典が地元の人たちによって守られたことが分かります。


また左の様に各巻の裏には「家内安全の為」等の願文と共に寄進者が書かれています(これには比土村の三名の名が見えます)。広く阿保周辺の村々がお金を出しあい寄進した事がうかがわれます。
また右の巻には明治十七年から大正五年にかけ古くなり糊が切れバラバラになりかけたので修理したとあり、近年に至るまで大般若経転読会に使われ大切にされたいた事があ分かります。