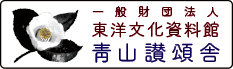初夏の企画展新指定 伊賀市文化財 若宮八幡神像 初公開「神が息づき仏が導く~穐月明と仏教美術の世界」は終了しました。
2024.5/17 ㊎~ 6/17 ㊊ 火曜日休館

■ギャラリートーク「神と仏と山と川と」
穐月明の神仏と自然への想いを中心に展示解説をします。
【日 時】 6月2日㊐13:30~
【場 所】 伊賀市 ミュージアム青山讃頌舎
【解 説】 学芸員 穐月大介
*予約不要。参加は無料ですが入館料が必要です。
■ 文化財を訪ねて「大村神社と阿保宿周辺ウォーク」
阿保周辺に残る文化財を特別拝観を交え巡ります
【日 時】 5月26日㊐
【集 合】 伊賀市 ミュージアム青山讃頌舎受付13:00
【行 程】 徒歩/伊賀市 ミュージアム青山讃頌舎~大村神社~柏尾~寺脇宝厳寺~初瀬街道交流の館 たわらや~伊賀市 ミュージアム青山讃頌舎
【案 内】 学芸員 穐月大介【定員】 20名【参加費】 500円(観覧券込み)
【申込先】 要予約 青山ホール受付 ☎0595-52-1109
穐月明と仏教美術の世界
故穐月明旧蔵の古美術は伊賀市に寄贈されたものの評価が定まっていませんでしたが、その一つ「若宮八幡神像」が昨年、伊賀市の文化財指定を受けました。その公開に合わせて、生涯を通し集めた仏教美術の優品と神仏をテーマとした作品を展示し、穐月明が見ていた神仏の世界をご覧いただきます。また、隣接する大村神社・虫喰鐘も昨年、伊賀市文化財に指定されました。虫喰鐘は大村神社の神宮寺であった禅定寺の鐘だったものです。禅定寺に関わる文化財を同時に紹介し地元に残る神仏の世界の一端を紹介致します。

伊賀市指定文化財若宮八幡神像
絹本著色・鎌倉時代( 十四世紀)
本図は令和五年三月二十日付けで伊賀市指定文化財となりました。
この若宮八幡神像は麹塵袍という天皇の装束を着用した若き貴公子姿であらわされ、祭神論からすると、八幡大神(応神天皇)の子息・仁徳天皇に当たります。
画面右上に「和光同塵 結縁之初 八相成道 以為其終」とあるのは仏が親しみやすい神の姿を取って衆生と縁を結ぶと解せられて本地垂迹思想を表しています。
本図とほぼ同図の作品としては鎌倉国宝館蔵の重要美術品「若宮八幡神像」が知られますが、本図の方がやや下向き加減で、愁いを帯びた表現で、むしろ習熟した絵師の手になると考えられます。

金銅仏
中国唐時代
銅の鋳造仏に鍍金をした仏です。『日本書紀』に六世紀半ばに百済から初めてもたらされた仏像が金銅仏であったとされます。

古鏡
伊賀市蔵(穐月明旧蔵)
右から
・蟠螭文鏡(中国春秋戦国) 竜が絡まった文様です。
・方格規矩獣文鏡(中国漢) 周囲に四神等を配し中央に十二支の漢字が記されています。
・画文帯同向式神獣鏡(中国後漢) 周囲に道教の神と神獣を配しています。同種の鏡は日本の古墳からも出土します。
・海獣葡萄鏡(中国唐) 海獣とは海外の獣(ライオン等)のことで、葡萄は多産と豊穣の象徴です。正倉院の宝物としても知られています。
・対鳥竜文八花鏡 中国唐鏡でしょうか、綬をくわえた鳥を左右に配し、下部に龍、上部に月の中に桂の木を挟んでウサギが描かれています。

鐘声月天子
穐月 明
「月天子に帰命し奉る、その本地は勢至菩薩で衆生を救うため、普く天下を照らす。一称一礼する者、罪を滅し苦悩を除き現世は安穏楽に、臨終は正念に住し安楽国に往生す。」
ここでは月(月天子)の正体を勢至菩薩としています。

念持仏
江戸時代
個人が身辺に置く私的な仏像です。小さな物は携帯できるようになっており枕仏とも言います。
拡大しても粗が見えない細工の細かさや衣の截金に驚かされます。
・三天念持仏(摩利支天・弁才天・大黒天)江戸時代に三天と称され蓄財と福徳の神として、特に商工業者の 間に信仰されました。

大正新脩大蔵経
大正十三年から十年間をかけて日本で編纂した大蔵経で、高麗大蔵経を底本としつつ日本の漢訳仏典をすべて調査し、まとめられました。大蔵経とは経・律・論(三蔵)を含むすべての経典の集大成です。
穐月明の仏書コレクションは高麗大蔵経、南伝大蔵経、乾隆大蔵経など膨大です。

弁財天曼荼羅
室町時代
弁財天はインドの川の女神を起源を持つ天部の仏です。日本では宇賀神と集合したり七福神に取り入れられるなどし神社の祭神にもなります。此の図も頭に宇賀神を頂いています。
図下部に十五童子を従え、、足下に毘沙門天と大黒天、上部に役行者と神像を配しています

福徳弁才天
穐月 明
おなじみの腕が二本で琵琶を弾く弁財天です。
背後に川の女神としての川が描かれ、財宝神としての小判や宝珠、宇賀神を意識した蛇も描かれています。琵琶は勿論、音楽芸能の神を表します。

毘沙門天像
江戸時代
多くの毘沙門天は左手に宝塔を持つ姿で表されますがこの像は左手に戟だけを持っています。
財宝神でもあり七福神の一つに数えられ、四天王の一尊としては多聞天と呼ばれます。
毘沙門天(穐月 明)
左手に宝塔を持つ、よく見る毘沙門天を穐月明らしくコミカルに描いています。
自分の主人を支えている夜叉の一途な表情も楽しい作品です。

青面金剛
江戸〜明治時代
もともと仏教の鬼神ですが、庚申待の本尊とされ民間に定着しました。
庚申待は庚申の日、人が寝ると三戸の虫が体から抜け出し、天帝に罪を告げるとう道教思想が中国から伝わり、その日は寝ずに夜を明かす風習です。
青面金剛と三猿を彫った庚申塔はこの周辺にもたくさ有ります。

大村神社—虫喰鐘の伊賀市文化財指定によせて—
当館に隣接する大村神社は広く阿保地域の氏神・大村の神をお祀りする神社ですが、明治になるまではここにも別当寺として禅定寺という寺院が隣接していました。この度、若宮八幡神像と共に伊賀市文化財に指定されました虫喰鐘はその禅定寺の鐘でした。またその禅定寺の本尊だった十一面観音菩薩立像は近郊(寺脇)の宝厳寺に移され、国重要文化財に指定されています。
一方、大村神社は宝殿が国重要文化財に指定されており、大村神社を中心に様々な文化財や伝承、行事が受け継がれています。
まさに神が息づき仏が導く所であった大村神社と、ここに関わる文化と文化財をご紹介致します。

国重要文化財・大村神社宝殿
木造・安土桃山時代
宝殿は大村神社主殿であった鹿島社が現在まで残されたものです。天正九年天正伊賀の乱の兵火によって焼かれた主殿は同十五年に再建され、豪放華麗な桃山様式の建築美が残されました。
正保四年、元禄十一年、安永八年の棟札三枚も合わせて国指定とされています。

大村神社宝殿棟札
棟札には再建・修復に関わった庄屋や、大工、屋根葺き、絵師などの名前、その諸費用の明細なども書かれています。しかし禅定寺別当の名前は後世に墨で消されたようです。
また正保四年の棟札には神社再建の事情や、その時の取り決めなども書かれています。

伊賀市指定文化財
大村神社梵鐘
江戸時代
梵鐘は令和四年三月十八日に伊賀市の文化財指定を受けました。乳とその周辺が腐食されている事から「虫鐘鐘」と呼ばれます。
梵鐘の銘文に製作は明暦二年(一六五六)、鋳造は依那具村の鋳工、発願は禅定寺の覚祐、施主は大村神社の秋長康正や周辺七ヶ村の庄屋・年寄等です。元は大村神社神宮寺だった禅定寺のもので、明治のはじめに廃寺となり梵鐘が残りました。銘文に製作年が銘記され当地で発願・施工された詳細も確認でき、江戸前期の大村神社と氏子の関係をうかがえる貴重なものです。
伝承は鋳造の時、魔鏡を鋳込みそのため持ち主の娘が死んでしまいます。其の祟りで乳が虫が食ったようにぼろぼろと落ちていったとと言うお話です。
奇鐘として初瀬街道の名物だったようです。

宝厳寺
創建は九世紀(平安初期)という伝承が有りますが不明です。しかし鎌倉時代には確かに寺が有ったようです。地蔵菩薩を本尊とし地蔵堂とも呼ばれ古くから当地方の地蔵講の中心であったようです。
本尊は秘仏で水晶の玉に入った地蔵菩薩と伝わり、境内にはたくさんの地蔵石仏が有ります。
当寺には明治の神仏分離で廃寺となった大村神社の神宮寺・禅定寺の「本尊十一面観音立像(国重文)」「大般若経六百巻写経本」「三仏像・三神像木造厨子」が遷れました。これはのち長老大僧正で西大寺管長となった真応住職が中心になって保護したようです。
その経緯は大般若経六百巻写経本奥書に詳しく書かれています。

国重要文化財
宝厳寺 十一面観音立像
木造・平安時代
元大村神社の神宮寺・禅定寺の本尊で旧国宝です。
榧材の一木造り、元から全体は素地で、唇に朱、眉目・口元には墨彩をさしていたようです。
裾の上方に結び目のあるのが特徴的で、平安前期の様式を多分に残した平安後期の作ともみられます。

宝厳寺 写本大般若経六百巻(内一〜百巻)
紙本・江戸初期
第一巻につぎのような由緒が奥書に、この経を南都(興福寺)真福寺で貞享一年に書写されたとあります。また、各巻の奥書には寄進した村々の人の名前が有ります。続いて、経巻が禅定寺から宝厳寺に移った経緯が朱書されています。以下要約です。
「・江戸時代、この大般若経は大村神社の本殿の中に納められていたが、維新政府の神仏分離令で別当寺であった禅定寺へ引上げられた。
・その後に始まった寺院整理で禅定寺は明治三年廃寺となった。
・その時、本尊十一面観音立像と三仏厨子は宝厳寺が預かることになっが、大村神社の氏子が大般若経を売却しようとしたので宝厳寺住職は「その値段で当寺が譲り受けよう」と申し出た。
・ところが、氏子の中の不心得者が勝手に十円で他へ売ってしまった。
・そこで、檀家たちが相談し、買主に交渉、当寺所蔵の木版の大般若経と交換ということで、ようやくこの由緒ある写経本を確保することができた。
と有り、村々が寄進した地域の宝を守った人たちの熱意を感じます。」
大般若経守護十六善神図
穐月 明 伊賀市蔵
十六善神は玄奘三蔵が持ち帰った大般若経を守護する四天王と十二神将で、大般若経を唱える者も守るとされ、村々で購入し大般若会(転読会)が開かれました。
図には中央に釈迦と文殊菩薩、普賢菩薩、それを十六善神が囲み、玄奘三蔵(三蔵法師)と深沙大将(沙悟浄に当たる)が描かれ、大般若会に掛けられます。