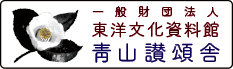ギャラリートーク/教 授 と 学 生 のアートトーク
「いまに息づく桃山陶器~桃山デザイン展 in 伊賀~」は、京都市立芸術大学で開講されている「テーマ演習(考古楽 桃山デザイン)」の成果としての展覧会です。
学生たちは、桃山陶器の考古学を楽しく学びながら、そのデザインの面白さに着想を得た作品を制作しました。本展では、その作品と元となった陶磁器をあわせて展示しています。
はじめに、今回のギャラリートークでは、指導を担当された畑中教授から、桃山時代の自由で豊かな時代背景や、そこから生まれた日本初の絵付け陶器/美濃焼や唐津焼の“ゆる〜い”文様についてのお話がありました。

「豊国祭礼図屏風」の前で、教授と学生の話に耳を傾けるギャラリートークの聴衆。

畑中教授は、「京都せと物屋町」から出土した織部焼を前に、桃山陶器誕生の背景や、初めて絵付けをした陶工たちがどのように“ゆる〜い柄”を生み出していったのかを語られました。

今回、特別出展してくださった小島憲二先生もギャラリートークに参加されました。

小島憲二先生作「古伊賀オマージュ花入」。伊賀焼きにしばしば見られる“割れ”をモチーフにした花器。

入り口に設置されたモニターで上映されているアニメーション作品「虫ウサギの1日」を自ら解説する作者。

食べて寝るだけの「虫ウサギの1日」。ムシウサギは桃山陶器にしばしば登場する謎の生き物です。

「桃山電鉄」の軸と「鴛鴦(おしどり)」を前に制作当時のことを語る作者。「桃山電鉄」の軸は桃山陶器に現れるさまざまなユニークなキャラクターが描かれていますが、伏見桃山あたりの宇治川と京阪電車が元になっているそうです。

出土した陶磁器を組み合わせ作られた「鴛鴦(おしどり)」

可愛いムシウサギのオリジナルTシャツを着た作者。作品は「虫兎パンケーキ」クッションと、油彩「カフェオレ」「胡麻豆腐」。タイトルはすべて食べ物です。

虫兎パンケーキ」クッション

身長を超える巨大な虫ウサギのオブジェ「漆塗ムシウサギ」。
漆塗りは手間と時間がかかるため、制作は大変だったようです。作者が虫好きなことから、6本足の“虫体型”になってしまいました。
若い作者たちの制作に対する熱意と、心から楽しんで作品づくりをしている様子が伝わる、活気あふれるギャラリートークでした。