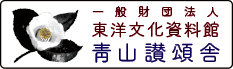伊賀市ミュージアム 青山讃頌舎 開館10周年特別展「いまに息づく桃山陶器~桃山デザイン展in伊賀~」は終了しました。
安土桃山モダンアート × 現代モダンアート 時空を超えたコラボレーション
2025/9/2/20㈯~10/19㈰ 火曜日休館


伊賀市 ミュージアム青山讃頌舎の前身である青山讃頌舎美術館を水墨画家故穐月明が開館してから10年となることを記念し特別展を開催します
桃山時代から江戸初期の「京都・三条せと物屋町跡」出土陶器は、丸みのある形や鮮やかな色彩、ゆるくユーモラスな文様が魅力です。本展では、そのデザインに注目し、古伊賀や豊国祭礼図屏風の複製、学生や現代作家による作品を展示。歴史と現代の感性が響き合う空間で、「もし自分なら?」と想像しながらお楽しみください。
本展では以下の作品を展示します。
・故奥知勇氏が収集し、三重県指定有形文化財に指定されている古伊賀
・「京都・三条せと物屋町跡」から出土した桃山時代の陶器、
・当時の様子をうかがい知ることができる京都豊国神社所蔵の「豊国祭礼図屏風」の高精密複製、
・桃山デザインにインスパイアされ制作した京都市立芸術大学の学生たちの作品
・伊賀を中心に活躍する陶芸家 小島憲二、天野靖史の作品
【桃山デザインとは】
京都市立芸術大学で開講されている「テーマ演習(考古楽 桃山デザイン)」にて、学生が桃山陶器の考古学を楽しく学び、その成果としてデザインに着想をえた作品を制作するという、芸術大学ならではの授業のなかで名付けられました。

ギャラリートーク
京都市立芸術大学の考古学を専門とする教授と学生によるギャラリートークを開催いたします。桃山デザインの楽しみ方や、作品への想いを語ります。
日時:10月12日 (日)14時~
料金:無料(参観料は必要)、申込:不要
伊賀の魅力再発見!ワークショップ「木の実を食べる」
伊賀市ミュージアム青山讃頌舎周辺(伊賀青山)の豊かな自然を体感してもらえるよう、近郊で採れる自然の木の実を野外で調理し頂きます。
開催日:10月18日(土)
時間:10:00~14:00
料金:1800円
定員:15名集合場所:伊賀市 ミュージアム青山讚頌舎受付
案内人:穐月大介
問い合わせ先:伊賀市 ミュージアム青山讃頌舎
2090-9860-6432
メール:dakizuki@icloud.com
予約開始:9/1(日)より
予約方法:いがぶら・じゃらん・電話・mail いずれかにて


重要文化財「豊国祭礼圆屏風」(高精密複製)
六曲一奴紙本金地著色
慶長十一(一六〇六)年 狩野内膳筆
慶長9年(1604)、豊臣秀吉の七回忌にあわせて「豊国大明神臨時祭」という盛大なお祭りが行われた。その様子を描いたのが「豊国祭礼図屏風」で、社僧・神龍院焚舜の日記によると、この屏風は豊臣秀頼が家臣の片桐且元に作らせ、2年後の慶長11年(1606)に豊国社へ奉納されたことが分かる。片桐且元は祭礼の企画にも関わっており、この屏風は豊臣家が公式に残した祭礼の記録といえる。
かぶり物を着て踊りまくったり、飲んだくれて寝ていたり、自由奔放な祭の様子が描かれている。

古伊賀は代表的な桃山陶器で自由なデザインで知られます。
燒成
桃山陶器の中で食器から一線を画した窯場の一つが伊賀である。ここでは文様を描くことはないが、変形を効果的に用いた造形に加えて焼成においても従来になかった大きな革命的な試みが見られる。器面を端正なガラスで覆うという美観を備えた実用に供する「施釉」ではなく、質感(テクスチャー)の不均質さを表出するものとして用いる点。また、コゲを意図的に作り出し質感もさることながら視覚的に見るものを困惑させる。

伊賀焼の様な毛糸のコート

変形
桃山陶器の一つの特徴として変形がある。端正な円筒形で作り上げたものを意図的に歪ませること、最初から不整形な型に嵌め込んで自由な形状を志向している。一般的な心理としては端正な円形が安心する形状であると言われるが、左右非対称(アシンメトリー)に心惹かれるものがあるのは否めない。さらには焼成時に歪み割れたものにも美を感じており、桃山時代以降こういったものに高い評価が下されることが始まった。とりわけ伊賀をはじめとした焼締陶器の窯場で実践された故意に偶然に変形したものは、ただの形状の変化ではなく新しく意味づけられたものへの変身(メタモルフォーゼ)だと理解できる。
ムシウサギの展開

ゆるい図文
桃山陶器の図文は、決して達者な筆とは言いがたいが、下手の一言で片付けるのはあまりにも惜しまれる。実物を見ると、その筆の勢いに呑まれてしまうのだ。きまりから外れた図文は、破格の美とも呼ばれるが、現代の我々からすると「ゆるい」という言葉が適当のように思われる。どうやらいずれもが元になるものはあるようなのだが、陶工たちが写し崩し(ミストレーシング)ていったことがわかる。ほぼ原形をとどめていないものもあるのだが、それでもしっかりと流通している。新しい文様(ある種のメタモルフォーゼ)として理解し、受け入れていったのであろう。おおらかで好奇心旺盛な桃山時代の人々の姿が浮かぶようである図文の正誤も写し崩れも構わずに、筆を振るう職人の無邪気な様子を今も鮮やかに伝えてくれる。愛嬌のある図文に思わず笑みが溢れる気持ちは、今も昔も変わらないのだろう。

ムシウサギをキャラクターにしてクッションに

ムシウサギをアニメーションに

このウサギは肉食らしい。

ムシウサギの巨大な漆器のオブジェ
写し崩し/元が何だか分からない

写し崩し
故意に行なっているのか、仕様がとてつもなくいい加減だったのか、それとも技量があまりにも低すぎたのか、原型は存在するものの、その存在がうっすらとしか分からない図文がある。美濃と唐津を比較すると、前者は手本を見ながら描いているが、後者は「こんな感じのものを」という伝言ゲームで描いているかのようなものが多い。故意に行なっているならば、まさしくミストレーシングであり、面白いとしか言いようがない。こういったものは伝世品をはじめ各地の遺跡からも出土しており、受け入れられていたことは確実である。
京都市立芸術大学のテーマ演習においてはミルクボーイの漫才に乗せながら誤読を繰り返しながら新しいものを創造するプラクティスを行った。

聞き違いを繰り返し桃山時代に鉄道が有ったらしいと言う世界を。
千鳥・鳥・色とり鳥


千鳥の暖簾?雀もハシビロコウもインコもいる・・・

桃山〜江戸時代の陶器破片が合体!オシドリに。

これも鳥、桃山陶器に描かれたの鷺(サギ)らしい
架空の工芸品

豊臣秀吉が実子秀頼のために作らせたベビーカーと言う設定の工芸品。伊勢神宮の式年遷宮をお祝いする「依代」を公募した依代アートプロジェクト入選作品