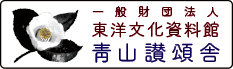11/16(日)、開館10周年記念特別展「大観 玉堂 龍子 近代日本画三大巨匠」展/ギャラリートーク開催
開館10周年記念特別展「大観 玉堂 龍子 近代日本画三大巨匠」
横山大観 川合玉堂 川端龍子 展
2025/11/14㈮~12/15㈪
今回の記念特別展はパラミタミュージアムのご好意により横山大観 川合玉堂 川端龍子 作品計16点をお借りし、展示しています。また、それと並行して当館の穐月明作品6点も展示致しました。

11/16(土)のギャラリートークはパラミタミュージアムの学芸部長 衣斐唯子先生にご講演いただきました。
江戸から明治となり、横山大観 川合玉堂 川端龍子はそれぞれ異なる活動の場を持ちながらも、互いに交流し刺激を与えながら、三者三様の画境を切り開き、近代日本画を作り上げていきました。
そんな3人3様のお話をさまざまなエピソードを交えながら楽しく作品を解説してくださいました。

川合玉堂は四条派の柔らかな写生表現に、狩野派の精神性と構成力を融合させ、美しい墨線と彩色で四季の山河とそこに生きる人々や動物を描いた、叙情性豊かな風景画で知られています。
玉堂がラジオ出演することになった時、真面目な玉堂はガチガチに緊張していたそうです。そこで、共演することになっていた龍子が一杯飲ませて落ち着かせたそうです。

横山大観は日本美術院の創設者岡倉天心の指導を受け、日本画の新しい表現を切り開き近代日本画を先導した日本画革新の中心人物です。岡倉天心から空気を表現するというテーマを出され、従来の輪郭を描き彩色する技法から、輪郭を廃し、色のぼかしによって空気感を表す新しい画法「朦朧体」を生み出したエピソードは有名です。
大観と玉堂は2人が、共通の友人の娘さんから絵を描いて欲しいとせがまれた際、玉堂はなかなか描いてくれなかったのに、大観はいくらでも描いてくれたそうです。

元々洋画を志していた龍子は日本画に転向し日本美術院に参加しました。当初10歳以上年下の龍子を大観は大変可愛がりますが、斬新で激しい筆致の龍子はやがて「床の間の芸術」としての日本画に対し公共の場で民衆に訴える「会場芸術」を提唱して自ら「青龍社」を創立し、離れていきます。
龍子は大観から離れても正月には大観の軸を掛け、その恩を忘れていなかったそうです。晩年そんな2人を再び引き合わせた人物がおり、大観・玉堂・龍子の3人は共同でテーマ(雪月花、松竹梅)を決め3人展を開催しました。この展覧会は玉堂がなくなるまで6年間続きました。

衣斐先生はパネルを持ってきてくださり、丁寧に説明してくださいました。これは龍子の三重県のお寺にある天井画です。
本展覧会では大観・玉堂・龍子それぞれが富士山を描いています。これを見ると3人3様の方向性が見えてくるようです。

横山大観の「神国日本」は輪郭を廃し墨の濃淡で富士を立体的に描いた作品です。神々しい雲海が広がる中に純白の冠雪が映え、濃い色で描かれた峰のコントラストが美しい富士です。愛国心の強い大観にとって富士は神国日本の精神を象徴的に示す重要な題材でした。

玉堂の富士はそこに生きる人々の営みと一体となった詩情あふれる情景の背景として描かれています。しっかりとした写生を基礎に狩野派に学んだ巧みな水墨の筆致が際立っています。小さいながらイキイキした人物が描き入れられているのも玉堂らしい作品です。

龍子の富士は大胆なタッチと、印象派を思わせる色彩で少し抽象化された富士と雁を描いています。元々洋画を目指していた龍子らしい斬新な作風です。
穐月明作品も展示いたしました。
穐月明はこの3人と入れちがうように、昭和30年ころより水墨画家としての活動を始めました。彼らの画法を学びつつも、当時形成されていた画壇に背を向け、独自の水墨画を目指しました。フェノロサが否定した文人画的な書画一体の画風を目指し、仏教、老荘思想、文学などから題材を取りつつ、輪郭を意識しない立体感のある石仏や花、空気感や水の流れを感じる山村風景などを先人とはまた違う手法で描き出しました。また、可愛さ、優しさ、安らぎ、ユーモアを感じられるのも特徴で、今日的な共感を呼びます。

穐月明「月の池」は墨の濃淡だけで描かれています。煌々と月明かりに照らされた池は明るく描かれ、月は周りを暗くすることで月の輝きが強調されて、明るい絵であるにも関わらず月夜らしさが溢れています。湖面に映る月は一匹の水鳥が泳いできて崩し、キラキラと輝いています。月夜の静寂とひんやりとした空気感を感じさせる作品です。

穐月明「御堂讃」は墨画に彩色を施した作品です。森のお堂に集まってきているのは花を供えにきた動物たちです。森で修行し真理を極める仏教本来の姿を、可愛らしい動物たちと共に描いています。書かれている賛は「仏前勤行次第」です。ほのぼのとした優しさを感じる作品です。